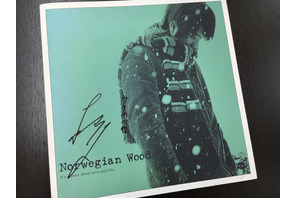【MOVIEブログ】2020年ベルリン映画祭 Day4
23日、日曜日。朝は曇り、気温は10度くらいあるかも? 暖かいとまではいかないものの、寒くはない。キリキリした寒さの例年のベルリンが恋しい。
最新ニュース
スクープ
-

満島ひかり×岡田将生共演『ラストマイル』あらすじ・キャスト・公開日【4月19日更新】
-

【MOVIEブログ】2020年ベルリン映画祭 Day3
-

≪配信開始≫チュ・ジフン×ハン・ヒョジュ豪華初共演「支配種」は世界必見のノンストップ・サスペンス【PR】
本日も9時の上映からのスタートで、まずは「パノラマ部門」の『Wild Land』というデンマークの作品へ。両親を失った17歳の少女が叔母の家に引き取られることになるが、その一家は反社会的な借金取り立てを生業としており、少女は犯罪と新しい家族への忠誠とのジレンマに苦しむことになる、というドラマ。
ヒロイン役の女優の不安げな佇まいや、一家を仕切る叔母を演じたデンマークを代表する女優のひとりであるサイズ・バベット・クヌッセンの堂々たる存在感など、作品の魅力は役者にあり、ぐいぐいと見せてはくれる。ただ、終わってみると、いくつか設定に難があったかと思わされ、最終的にはまずまずといったところかな。
続けて、12時からはコンペ部門で、ドイツのクリスチャン・ペツォルト監督新作『Undine』。歴史学者の女性ウンディーネは、不誠実な恋人に捨てられてしまうが、その直後に新たな男性と出会い、本当の関係を育んでいく…。
という要約では本作の5%しか説明したことにならず、愛のドラマであることは間違いものの、その内実は幾層ものレイヤーで構成されている。ペツォルト監督は、水の精霊として知られるウンディーネの神話を現代に置き換え、愛する存在を失った時に精霊の起こす行動に深い意味を持たせ、風格のある社会派メロドラマに挑んでいる。ペツォルト作品を一度の鑑賞で解釈するのは容易ではなく(いや、現代のバリを戦争状態とした前作『Transit』ほど難解ではないが)、今回はストレートな愛のドラマにも見えるがゆえに、深読みを誘われる。
本作のヒロインのオンディーヌが水と縁が深いことは序盤で明らかになり、彼女が新たに出会う男の職業はエンジニア・ダイバーで、ダムの水中に長時間潜り、電気系統などを修理することを日常としている。水を媒介にしてふたりは出会う。睡眠中に無呼吸になってしまう症状を俗に「オンディーヌの呪い」と呼ぶらしいけれど、水に繋がる窒息感が、物語の悲劇性を予感させていく。
いや、書いていて伝わらないなと思うので何が言いたいのかというと、とても素晴らしい作品であったということ。ヒロインがベルリンの歴史を博物館でレクチャーする場面が複数回登場し、壁崩壊から30年を記念するベルリンという都市の歴史が、本作の裏テーマになっていく。それを読み解くには、もう少し熟考と再見が必要だ。そして、ペツォルト特有というべきか、映像の色に品というか艶があり、作品の魅力を引き立てていく。さすが、ペツォルト。
思考を刺激されながら外に出ると、雨だ…。しかもかなり強い雨。こんなベルリンは初めてだなあ、とボヤきつつ、濡れながら移動して所用をこなし、一瞬ホテルに戻って体制を整えて、外へ(雨は止まない)。
15時半から、「特別ガラ上映」として出品されている、イタリアのマッテオ・ガローネ監督新作『Pinocchio』(写真)。数年前から話題になっており、あのマッテオ・ガローネがピノキオという有名な童話をどう映画化するのだろうかと期待が募っていた作品だ。
コンペ作品だと上映前に舞台挨拶はないのだけれど、「特別上映」は異なるようで(今年から映画祭のディレクターが交替したので、細かい変更点がたくさんある)、マッテオ・ガローネ監督に続き、ロベルト・ベニーニ始め主要キャストも登壇して華やかに盛り上がり、とても楽しい雰囲気。
そして、映画も実に素晴らしい。世界観は『五日物語 -3つの王国と3人の女-』(15)と地続きで、少しデルトロ的なダーク・ファンタジー風味も加わり、厳しいリアリズムを得意とするガローネのもうひとつの顔が堪能できる。もちろん、子どもが見られる配慮は行き届いているのだけれど、ピノキオの大冒険の道中に登場するキャラクターたちの造形の素晴らしさには、大人たちこそ狂喜するに違いない。
そしてなんといっても主人公であるピノキオの質感がたまらない。子役は連日4時間のメイクを耐えきったと冒頭の挨拶でメンションされていたけれど、顔の「木の肌触り感」のリアルさたるや。CG処理も加味されてはいるのだろうけれど、ここにガローネ一流のリアリズムを感じることも出来るかもしれない。木がきしむ音など、音響効果も楽しめる。日本公開がありますように!
続けて18時から「エンカウンター部門」のアメリカ映画で『Funny Face』という作品。ピノキオの幸せな世界から切り替えるのが大変だ。NYはブルックリンを舞台にした恋愛映画にして、高度資本主義社会を批判する社会派の側面を持ち、そしてその実態はミニマルで実験的な語り口を備えたアート性の極めて高い作品だった。
今年新設の「エンカウター部門」のテイストが次第に分かってきた気がするのだけど、新ディレクターのカルロは、彼の前職であるロカルノ映画祭のエッセンスを「エンカウンター部門」に注いでいるのではないかな。つまり、意欲的で、実験的で、刺激的である作品であり、規模感は問わない。この姿勢には共感するばかりだ。
『Funny Face』はNYを舞台にしていながら、どこか無国籍的な佇まいであり、そして映画全体を倦怠や終末感が覆う。しかしどこか甘美でもある。ティム・サットン監督、今後にも注目したい。
外に出ると、ようやく雨が止んだ。屋台のソーセージ、何故こんなに美味しいのか、と本日も感激しながら頂く。
22時からコンペ部門で、ブラジルの『All the Dead Ones』。むむー、これは期待を悪い方に裏切られてしまったか…。監督との縁は「予習ブログ」に書いた通りで、ブラジルのトレンドであるホラー風味の人間ドラマをどのように発展させているのか、相当に楽しみにしていたのだけれど…。室内の会話に終始し、著しくダイナミズムに欠けている。これは一体どうしたことか…。
あまり悪いことを衝動的に書くのは良くないので、一晩寝かせることにしよう。ちょっと考えなくては。そろそろ2時。寝ます!