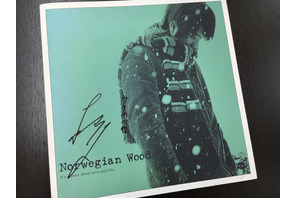【MOVIEブログ】20日&21日/カンヌ日記
20日、月曜日。晴れ、ただし風強く、気温も低い。週が明けるとマーケット周辺の人々はだんだんと帰り支度を始めるので、午前中は慌ただしくミーティングを7件ほど。
最新ニュース
スクープ
-

「結局何だった?」「伏線じゃなかったってことか…」“謎”が残った描写を振り返り「良いこと悪いこと」
-

【カンヌ国際映画祭】福山雅治、スタンディング・オベーションに「男泣き」
-

偽装夫婦の“嘘”のゆくえは? ラブコメ×サスペンスの後味が心地よい「私と結婚してくれますか?」
日刊紙の「リベラシオン」紙を買ってみると、どーんと是枝監督の『そして父になる』の映評が見開きで載っている(写真)。周りの業界人からもなかなかの好評が聞こえてくるので、こちらまで嬉しくなるのは人情。かくいう僕はまだ観ていないので、何ともリアクションが取れないのだけれど。
13時半から試写に行き、エストニア映画の非公開試写を連続して2本鑑賞。1本目は、内容は好きではないけれども監督のスタイルは認めたくなるタイプの作品で、2本目は予定調和の物語で監督の個性もあまりなく、2作品通じて1分け1敗、といったところ。
18時から、「アウト・オブ・コンペティション」(「コンペ」部門だけど賞の対象にはならないという、招待作品のような位置付け)のロシア映画で、『Bite the Dust』(英題)という作品へ。
昨日お茶をした日本の某配給会社のAさんがとても気に入っていたのを聞き、日頃からとても好みが合う方だったので(大先輩なのでこんな言い方はおこがましいけれど)、本日追加試写があるのを知って慌てて観に行ったのでした。が、僕はイマイチでした! Aさん、ごめんなさい!
ロシアの片田舎の極少コミュニティーを舞台にした、風変りなファンタジー作品で、地球の終りが宣告された後の終末観が漂う世界を描くダーク・コメディーといったところ。結局はいくつかのカップルの恋愛を含めたバタバタ劇になってしまっているところが僕には少し残念で、でも大水に流される家々や、細かい小道具に至る美術がなかなか凝っていて、観ていて楽しい作品ではありました。
夜は上映を休止して、日本の方々との会食へ。是枝監督も参加なさっており、僕は10年ほど前にお会いしたことがあるだけなのでその時のことをお話ししたり、そしてもちろん今回のカンヌのご感想なども伺うことができて、とても幸せで有意義な夜になった!
とても美味なワインをたくさん飲みすぎ、終盤は襲い掛かってきた眠気と闘いながら(少し負けた)、0時過ぎにお開きで、ホテルに戻って即ダウン。
明けて、21日火曜日。今朝も快晴。でも、やはりかなり肌寒く、上着は欠かせず。ホテルでバゲットパンにジャムを塗って、外に出てそれをかじりながら上映会場へ。
見たのは、8時半から「批評家週間」部門で『The Owners』(英題)というアルゼンチン映画。屋敷に暮らす若いブルジョワ夫婦と、労働者である使用人たちとの関係を描き、現代の階級衝突の矛盾を突く物語。と書いてしまうと重苦しい印象を与えてしまうかもしれないけれど、基本的にはオーソドックスな描写の風通しのよいドラマで、新人監督としてはまずまず、かな。
10時半から、5件ミーティング。かなり良さそうな作品情報を得られたので、少し興奮。うまくいくといいなあ。13時に、ビュッフェ形式の中華料理店に行き、10分でランチを呑みこんで、14時からの上映の列へ。
「ある視点」部門で、クレール・ドゥニ監督新作の『Basterds』(英題;仏題は『Les Salauds』)。クレール・ドゥニは僕の人生を変えた監督のひとりでもあり(大げさですね)、ドゥニの新作とあれば僕はもう何がどうあっても見たい。なので、今年のカンヌの個人的なハイライトのひとつでもあるのでした。
主演は、ヴァンサン・ランドンとキアラ・マストロヤンニ。ヴァンサン・ランドンは、これまた僕が偏愛する俳優のひとりで、最近の彼の出演作にハズレはないのではないかと思うくらい。僕の記憶に間違いがなければ、ドゥニ作品にランドンが出るのは、渋滞をきっかけに行きずりの肉体関係が生まれる様を濃密に描いた傑作『Vendredi Soir』以来で、ほぼ10年振りのはず。これは期待が高まらずにいられない。
実は、前作の『White Material』(イザベル・ユペール主演でアフリカが舞台)が珍しくピンと来なかったので、多少の心配があったのは確かなのだけれど、今作ではその心配は杞憂に終わり、ドゥニ節がたっぷり発揮された「復活作」になっていた。僕は舐めるように映像を堪能するばかり。
ただ、会場の反応はいささか鈍く、それは物語が少し雑であるから、かもしれない。ランドンの姉の夫が自殺し、その自殺への関与が推察される財界の大物の正体を暴くべく、ランドンが大物の愛人に接近するという物語で、いささか展開が強引であり、物語だけを追っている人には物足りなく映ってしまうかもしれない。
ただ、昔も今も、ドゥニが描きたいのは物語ではなく、肉体である。存在理由としての肉体であり(『Beau Travail』)、セックスの肉体であり(『Vendredi Soir』)、果ては食用の肉体であり(『ガーゴイル』)、つまりは肉体そのものなのだ。本作でも、盟友アニエス・ゴダールのキャメラは冴えまくり、アップの多用で表情から心理を掬い取り、そのまま肉厚のランドンの背中がキアラ・マストロヤンニ覆いかぶさる様を陰影で描いていくタッチは、まさにクレール・ドゥニの本領が発揮された世界であり、独壇場だ。
セックスを見せるためのセックスシーンでなく、肉体そのものに迫ることを目的とするセックスシーンを、映画は描くべきであると僕は思うのだけれど、その点においてクレール・ドゥニは唯一無二の存在であると改めて確信。
肉体が完膚なきまでに傷付けられる非情で残酷なエンディング。そこには感情の関与がもはや許されないほどであり、肉体に迫りながらそれを相対化するというドゥニの世界のひとつの到達点があるのではないかとさえ、僕は思ってしまう。作品単体での評価は厳しいものが出てきてしまうかもしれないけれど、ひとりの作家の系譜として見ると、僕は深いもう深い感動と戦慄を覚えざるをえない…。
ぼうっとしながら会場を出て、すぐに16時半から、「ある視点」部門で『Wakolda』(原題)というアルゼンチンの作品へ。50年代を舞台にした、アルゼンチンに逃れていたナチのマッド・サイエンティストの行状を描く物語。オーソドックスで安定したドラマ作品だけれども、アーティスティックなチャレンジはいささか希薄。
上映終わっていったん宿に帰り、少しパソコン仕事。
21時に蝶ネクタイを締めて、メインのコンペの会場へ。とても楽しみにしていた、イタリアの鬼才パオロ・ソレンティーノの新作『The Great Beauty』(英題)へ。
今回は知り合いのイタリア映画関係者から招待状チケットをもらったのだけれど、行ってみたら考えられないようなVIP席でビビった! 場違い感満載の気持ちで、小さくなりながらスクリーンに映し出されるレッド・カーペットの中継を見ていると、なんとレオス・カラックスとカイリー・ミノーグが登場!タキシード姿の人々に交じり、レオスは完全に普段着。カッコ良すぎる…。ヴァンサン・ランドンとクレール・ドゥニも来場。おお。結局僕はソレンティーノ監督の3列後ろで、全くこんな席に座るなんて後にも先にもないだろうな。
今作はイタリアに舞台を戻し(前作の『きっとここが帰る場所』はアメリカ)、主演のトニ・セルヴィッロ扮する作家の心的な体験をイマジネーション豊かに描く抒情詩な作品。難解なセリフにとまどうところはあるものの、とにかく映像と音響が圧倒的なスケールで甘美であり、想像力を全開にしながら心をゆだねるのみ。美しい。
終わって0時半。宿に戻って、ビール飲みながら(ごめんなさい)ふらふらとこれを書いて、そろそろ2時。限界見えたので、ダウン!