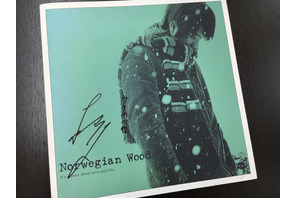【MOVIEブログ】2015カンヌ映画祭 総括(のようなもの)
カンヌ映画祭が無事終了しました。12日間の長丁場ですが、実際に滞在しているとあっという間で、振り返ると一瞬の出来事のようです。今年も素晴らしい作品が多く揃った充実の映画祭でした。記憶が新鮮なうちに、総括的な感想を書いてみようと思います(超長文御免!)。
最新ニュース
スクープ
-

プロが選んだ韓国ドラマ2025年ベスト5【ラブコメ】年末年始イッキ見オススメ
-

【カンヌ国際映画祭】パルムドールにジャック・オディアール監督『ディーパン』
-

偽装夫婦の“嘘”のゆくえは? ラブコメ×サスペンスの後味が心地よい「私と結婚してくれますか?」
なんといっても、ハイライトとなるコンペティションの受賞結果から触れないといけないでしょう。1等賞のパルムドールを受賞したのは、ジャック・オーディアール監督の『Dheepan』(写真)でした。これは、カンヌで12日間を過ごした参加者の誰一人として予想しなかった結果で、僕も腰が抜けるほど驚きました。
フランス映画が多く受賞したことを揶揄する向きもあるようですが(パルムドールと、主演男優賞と主演女優賞がフランス映画)、審査員にフランス人が多いわけではないので、これはどうこう言ってもしょうがないでしょう。そもそもコンペ部門にフランス映画が多すぎることも指摘されていましたが、個々の作品は(ほぼ)全てクオリティーが高く、数の多さ自体に違和感を覚えることはありません。
下馬評として話題にあがっていたのは、ソレンティーノの『YOUTH』であり、トッド・ヘインズの『CAROL』であり、ナンニ・モレッティの『My Mother』であり、ハンガリーの新人監督による『Son of Saul』であり、はたまたホウ・シャオシェンの『The Assassin』であったりしました。『Dheepan』が話題に上ることはなく、あったとしても、今までのオーディアール作品と比べていささか劣るのではないかという指摘や、あまりにもとってつけたようなエンディングに対する不満などであり、前向きな感想が交わされることはありませんでした。
それだけに驚きは巨大でした。たかが映画祭の受賞結果に対して騒ぎ過ぎるのもいかがなものか、ということを自覚はしているのですが、12日間連続でどっぷりと早朝から深夜まで映画祭に浸かった身からすると、心身を捧げた濃密な時間を、ある意味で総括することにもなる受賞結果のインパクトは大きく、まるで自分のことのように動揺するものです。カンヌのパルムドールの結果にこれほど驚きを覚えるのは、近年では記憶にありません。『ホーリー・モーターズ』が無冠に終わった年も相当落胆しましたが、その年にパルムを受賞した『愛、アムール』に不満があったわけではないので、今回の驚きとはちょっと種類が違うようです。
『Dheepan』の感想については出張中のブログに書いたので繰り返さないですが、ともかく作品として悪いわけではないけれど、オーディアールの中では特に秀でた1本ではないというのが大方の反応で、僕もその意見に与するひとりです。完成度は高いけれども、一昨年のパルムドールの『アデル、ブルーは熱い色』や、昨年の『雪の轍』が備えていた圧倒的なインパクトはなく、過去の受賞作と比べるとごく普通の作品にしか見えない。ではどうしてこの作品が最高賞を受賞したのか。
正直なところ、全く分かりません。ただ、敢えて想像できる理由はふたつあり、ひとつはジャック・オーディアールという監督のネームに対する受賞であるということ。欧州においてオーディアールに寄せられる敬意は日本では想像できないほど大きく、最も重要な映画作家のひとりと言っても過言ではない位置にいます。過去に審査員賞を受賞していることもあり、「そろそろパルムドールを」という流れがあったかもしれない。
もっとも、本当にそんなこと(監督のキャリア)が作品の審査を左右する要素になるものかねえ、と僕は自分で書いておきながら懐疑的です。それよりも、この作品が扱っているテーマが決定的だったのではないかというのが、想像するふたつめの理由です。
アフリカや中東からの移民の流入が現代ヨーロッパの最重要課題のひとつとなって久しいですが、歩調を合わせるようにして映画にも「移民もの」や「越境もの」が各国にて非常に多く作られており、もはやひとつのジャンルを形成しています。と冷静に書いている場合ではなくて、イタリア沿岸では大量の死者を乗せた船が捕獲されることも多く、より踏み込んだ人道的対策の必要性が叫ばれる一方で、移民増加の反動で極右政党が各国で躍進するなど、移民問題が欧州全土を揺るがす要因になっている。日本からは完全に対岸の火事状態で、その温度差は如何ともしがたいですが、「いまそこにある危機」が移民を巡って欧州には存在しています。この状況を映画が描くのは必然であり、その数はますます増えているという実感があります。
ここで、移民を巡る状況が極端な形で爆発したのが、1月のシャルリー・エブド襲撃事件であったことを思い出す必要があるでしょう。風刺画を掲載した新聞社をアルジェリア系移民が襲撃し、複数の死者を出した事件は世界に莫大なる衝撃を与え、各国首脳が集まって抗議の行進をするという事態にまで発展したのは記憶に新しいところです。この事件には幾重もの側面があり、表現の自由を巡る議論とともに、アルジェリア系フランス人に対する日常的な差別の存在も事件の背景として議論されることも多く、移民と社会の融合の難しさを象徴する事件となりました。
そこに登場したのが『Dheepan』だったのかもしれません。郊外の低所得者用団地に集められる移民たち。犯罪の温床となり、明るい未来を描くことの困難な環境。昨今の映画が多く背景として用いてきたこの環境下で、『Dheepan』も展開します。内戦の続くスリランカから脱出してフランスに移住した主人公のディーパンが、地に足を付けた生活をしようと地道に働くものの、団地を根城にするチンピラヤクザ集団の抗争に巻き込まれ、運命に翻弄される様を映画は描きます。
移民と社会の融合の難しさが具体的大事件として勃発した年に、尊敬を集める監督がまさに同じテーマで水準作を完成させた、という点が今年のパルムドールの決め手ではなかったか、というのが僕の想像です。映画が社会を反映する鏡であり、カンヌ映画祭が映画に対してもたらす莫大な影響力を勘案すると、『Dheepan』はパルムドールを取るべくして取った、という見方ができるような気がします。
もっとも、社会的に重要なテーマを扱うことと、映画の出来とは、別の問題であるのは言うまでもありません。東日本大震災や原発事故を扱った映画が、全て傑作であるわけではない。つまり、「映画のテーマは映画の出来を正当化するか」という古くて新しい問いがここにはあるのであり、「移民もの」や「越境もの」にも面白くないものはいくらでも存在する。やはりオーディアール級の実力を備えた作家がこのテーマに取り組んだということが重要なのであり、現実社会とパラレルに繋がるフィクションを構築する力を、完璧なタイミングで発揮したことに対する賞であるという見方も出来るかもしれません。
リアリズムの手法で、過酷な国境越えや移住後の悲惨な状況を描く作家もいれば、『最強のふたり』に代表されるように、エンタメ系要素も配しながら現状を肯定的に描こうとする作家も存在します。今回のオーディアールはその中間に位置しますが、いずれにしても現代の意識的な作家にとって移民問題は避けて通れない主題であることは間違いありません。
コーエン兄弟率いる審査員チームが、どこまで映画祭サイドの意向を汲んでいるのか、全く想像するしかないですが、『Dheepan』の受賞はカンヌ映画祭が発信するメッセージとしては、とても重要であると言えます。カンヌ映画祭(カンヌに限らず本来映画祭たるもの全て)は、映画の素晴らしさを称揚するばかりの呑気な文化イベントではなく、意識的な作家を擁護する場です。それはすなわち映画祭自体が「政治」的になることを恐れないことであり、映画を通じて社会へのコミットメントのあり方を提示していくことでもあります。その意味で、『Dheepan』の受賞はカンヌの面目躍如と言えるかもしれません。いや、なんだか、書けば書くほどそうであるに違いないと思ってきました。
ただ、観客と言うのはわがままなもので、必ずしも映画に社会的価値を求めているわけではない。いや、もちろん求めてはいるのだけれど、それが映画の良さを正当化するわけではない。映画祭の意図(があるとして)を汲んだ審査員の判断と、観客の気持ちとに少しズレがあったことが、今回の結果が意外に受け取られることに繋がったのでしょう。
つまり今年は社会の状況が映画を引っ張った状態となり、50年代のダグラス・サークの世界を同性愛のメロドラマという形でトッド・ヘインズが完璧に再現した、あまりにも甘美な『CAROL』や、功成り名を遂げたブルジョワ老人が残りの人生を考える様を、ソレンティーノ特有のイメージ力を駆使して刺激的に描く『YOUTH』などは、観客は熱狂したものの、現代社会から乖離していると判断されてしまったのかもしれない。あるいは、病気の母親を心配しながら映画の撮影に臨む女性監督の姿が描かれる『My Mother』は、ナンニ・モレッティの私小説的映画に対する技が冴えまくった秀作であるにも関わらず、時代を超えた作品だからか(今年でなくてもよかった?)、今回は受賞と縁が無かった…。いや、これは全て邪推ですけどね。
ということで、パルムドールについてはこのくらいにして、他の受賞の特徴を見ると、やはり若返りが図られたということが言えます。今年はコンペ初参加監督が増え、常連の入れ替え(?)が意図されたことは以前のブログに書いた通りですが、受賞結果も見事にこのセレクションに応えた形となったようです。
2等賞であるグランプリは、ハンガリーの新人であるラズロ・ネメス監督の『Son of Saul』に与えられ、これは誰もが大納得の選出。監督1作目がコンペに入ったのも異例であるなら、それがグランプリを取ることもさらに異例。(というか、前例はあるのだろうか?)。ベラ・タールの助監督出身であり、フィルム撮影にこだわる映画作りをするネメス監督は、過去と未来の映画を繋ぐ希望の巨星であると断言します。
審査員賞は、ギリシャのヨルゴス・ランティモス監督の『The Lobster』に与えられました。僕も事前にとても楽しみにしていた1本で、嬉しい受賞です。ランティモス監督も、今後がますます期待される未来の鬼才候補。ねじれたブラックユーモアで現代社会の隙間を覗くような、独自の世界の構築が世界に認められつつある。90年代のカウリスマキや、ゼロ年代のロイ・アンダーソンのような、孤高の個性派作家のポジションを占めていくのはないでしょうか。
脚本賞は、スペインのミシェル・フランコ監督の『Chronic』へ。前2作がカンヌの他部門で評価され、3作目で初めてコンペ入り、そして受賞と、まさにカンヌが育てた才能として羽ばたいている。彼は次代のミヒャエル・ハネケのポジションと言ったら、単純化し過ぎかな?
繰り返すけれども、映画祭サイドの意向と、審査員の判断との間に、どのくらいの関係があるのかは、全く分からない。日本人でそれが分かるのは、一昨年審査員を務めた河瀬直美監督だけ。なので、印象で書くしかないのだけれど、3つの賞がコンペ初参加組に与えられたことは、コンペの風を変えたいと言う映画祭サイドの企図を大幅に尊重した結果になったのではないでしょうか。その流れの中で、マッテオ・ガローネや、パオロ・ソレンティーノなどの「新しい常連」たちは割りを食う形になったかもしれません。
とはいえ、映画祭では受賞の結果が全てではないこと、つまり、受賞していないから面白くないということは絶対にないということも、声を大にして主張しておきたい!審査員が変われば受賞結果もがらりと変わるというのが、映画祭の常です。
マッテオ・ガローネ監督『Tale of Tales』のファンタジー寓話も素敵だったし、ジョアキン・トリアー監督の『Louder Than Bombs』も好感度大、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督『Sicario』の緊張感もさすがで、ギヨーム・ニクルー監督『Valley of Love』の2大スター競演も素晴らしく、やはりこれだけ見応えのある作品が揃うコンペティションは、世界中でカンヌだけだという思いを改めて強くします。
他部門に目を向けると、好調が続く南米勢から、これまた好調のコロンビアの作品がふたつ賞を取ったのが注目されます。『Land and Shades』は全部門にまたがる新人賞のカメラ・ドールを受賞し、『The Embrace of the Serpent』が「監督週間」の賞を受賞しています。コロンビアは政府の助成も上手く機能しているようで、数年前から国内の映画業界が元気である印象を受けます。去年はトウキョウのコンペにコロンビアの作品が入りましたが、チリやメキシコに並び、南米勢の中で今後も要注目国です。
「ある視点」では黒沢監督が『岸辺の旅』で監督賞を受賞しましたが、やはりかなりレベルの高いラインアップでありました。僕は全部を見ることはできなかったけれども、アピチャッポン監督新作『Cemetary of Splender』は絶賛されていますし、ルーマニアのポロンボイユ監督『The Treasure』(「ある才能賞」受賞)も快作、はたまたクロアチアの『High Sun』(「審査員賞」受賞)を今年のカンヌのベストと推す声もあり、そしてアイスランドの『RAMS』は、多くの観客の絶賛の声を反映するかのように、「ある視点」部門の作品賞を受賞しています。
「監督週間」も、今年は例年以上に豊作であったというのが大方の意見の一致するところで、それはアルノー・デプレシャン監督の新たな傑作『My Golden Days』を従えていたということも大きいですが、その他にも、フィリップ・ガレル監督の軽妙にして格調高い『In The Shadow Of Women』、今年のカンヌで最も笑いの量が多かったジャコ・ヴァン・ドルメル監督の至福の『The Brand New Testament』、シネフィル的注目度の高さが一番だったミゲル・ゴメス監督の6時間越え3部作『Arabian Nights』、そして部門の作品賞受賞に異を唱える人が誰もいない納得のトルコの『Mustang』など、いずれもコンペ部門に入っていてもおかしくなく、今年のカンヌ全体のレベルの高さを象徴したのが「監督週間」でした。
さて、ここ数年、アジア勢の影が少し薄い印象があったカンヌですが、今年はなかなか健闘したのではないかというのが僕の印象です。コンペでホウ・シャオシャンが監督賞を受賞し、あらためてその存在感を世界に見せつけたことを頂点に、ジャ・ジャンクー監督新作『Mountains May Depart』も監督特有のスケールの大きさを備え、欧米作品と真っ向から張り合う力を持っていたし、ヒロカズ・コレエダ監督『海街diary』は爽やかな好意で受け止められていました。本当はコンペに韓国映画に是非入ってもらいたいところなのだけれど(ホン・サンス監督新作に期待していたものの残念ながら出品ならず)、来年は是非「中韓日」のそろい踏みを期待したいところです。
そして、他部門を見渡しても、クロサワ、カワゼ、アピチャッポン、ブリランテ・メンドーザなどの常連監督作品が軒並み好評、「ある視点」部門では韓国の新鋭が健闘し、インドの若手が紹介され、イラン映画も賞に絡みました。従って、今年のカンヌは、欧州勢を軸に、南米勢に並んでアジア勢もかなり目立ち、地域のバランスが上手く取れていたラインアップであったと見ることができそうです。しかし、一方で「監督週間」と「批評家週間」にアジア映画が非常に少ないという最近の傾向は今年も覆ることはなく、特に日本の若い名前をこれらの部門で見たいという思いは年々募るばかりです。
ふうー。いくら書いてもキリがないので、いい加減この辺でやめますね。ともかく、世界中で製作される作品のほんの一部しか紹介されないとしても、重要な映画の潮流が概観できるカンヌは、やはりとても貴重な機会です。日本での配給が決まったという報せも続々入ってきています。1本でも多く日本で劇場公開されることを祈りますし、東京国際映画祭でもフォローしていければと思っています。
ということで、まずは以上です。毎度のことですが、だらだらした長文にお付き合い下さり、ありがとうございました!