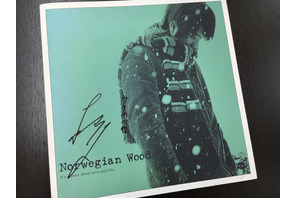【MOVIEブログ】2016カンヌ映画祭 総括
カンヌから24日に帰国しました。まだボケボケですが、ほとぼりが冷めないうちに、総括的な感想など書いてみます。長文になりそうなので、お許し下さい。
最新ニュース
スクープ
-

プロが選んだ韓国ドラマ2025年ベスト5【ラブコメ】年末年始イッキ見オススメ
-

「第69回カンヌ国際映画祭」パルムドールにケン・ローチ!次席はグザヴィエ・ドラン
-

偽装夫婦の“嘘”のゆくえは? ラブコメ×サスペンスの後味が心地よい「私と結婚してくれますか?」
【「コンペ」部門について】
ご案内の通り、最高賞のパルムドールはケン・ローチ監督『I, Daniel Blake』が受賞しました。僕は事前の予想にこそ挙げませんでしたが、ふり返ってみると文句の無い受賞ではあります。芯の通った社会派であり、巨匠ケン・ローチの面目躍如的秀作であることから、審査員としても妥結しやすい授賞だったのだろうと想像します。
しかし、ケン・ローチはさておき、全体としては、批評家筋やそのほか観客の事前の予想と、実際の結果とが今年ほどかけ離れた年は無いだろうというくらい、驚きの発表でした。愕然としたと言っても過言ではありません。念のため、コンペの主な受賞結果を下に記しておきます。
・パルムドール(1等賞):ケン・ローチ監督『I, Daniel Blake』
・グランプリ(2等賞):グザヴィエ・ドラン監督『It’s only the end of the world』
・審査員賞(3等賞):アンドレア・アーノルド監督『American Honey』
・監督賞:クリスチャン・ムンジウ監督(『The Graduation』)、オリヴィエ・アサイアス監督(『Personal Shopper』)ダブル受賞
・主演女優賞:ジャクリン・ホセ(『Ma’ Rosa』ブリランテ・メンドーサ監督)
・主演男優賞:シャハブ・ホセイニ(『The Salesman』アスガー・ファルハディ監督)
・脚本賞:『The Salesman』(アスガー・ファルハディ監督)
そもそも、映画祭のコンペ部門における賞は、外野の予想と合致しない場合の方が多いものです。映画の優劣を決めるのは難しく、絶対的な基準など存在しないから、審査員が変われば結果も変わります。であるにも関わらず、受賞を逃した作品は、まるで100m走でタイムが足りずメダルを逃した選手と同じような扱われ方をしてしまいます。100m走では計測時計を変えてもタイムは変わらないけれど、映画祭では審査員が変われば結果も変わる。なのに、映画祭の受賞の結果は、絶対的な結果として受け取られがちです。ウディ・アレンは賞に抵抗があり、カンヌに参加するときは非コンペを希望するのが通例で、今年も同様でした。
受賞の結果なんて審査員によって変わるし、時の運だから真剣に捉える必要もないし、コンペは最終日に向けて受賞予想で盛り上がるための装置と割り切ればいいじゃないか、と僕も思うことがありますが、受賞をすればその作品に箔が付き、宣伝に勢いを与え、監督の肩書にも重みが増す、という効果があるのは当然で、受賞した作品はそのメリットを存分に活用すればいいと思います。
しかし一方で、受賞しなかったからと言って、その作品が受賞した作品に比べて必ずしも劣っているわけではないのだということを、映画祭を良く知らない人にも分かってもらいたい。受賞作品に文句は言わないけど、特定の作品が受賞しなかったことには大いに文句を言いたい、というのが、今年のカンヌの結果に対する感想です。
昨年、大方の予想に反してジャック・オーディアールの『ディーパン』がパルムドールを受賞したことについて、何故かと問われた審査委員長のジョエル・コーエン監督はこう答えています。「カンヌは、映画批評家の審査員とは違うんです」。これはちょっと身もフタもない言い方ではありますが、まあこういうことなのでしょう。有名監督やスター俳優で構成されるカンヌのコンペの審査員は、とても豪華で、映画の作り手として確固たる実績を持つ人たちですが、映画の評価基準(というものがあるとして)に批評家と違いが出てしまうのは如何ともしがたいところです。
実際、今年の審査委員長のジョージ・ミラーがイラン映画にどれほどの知識があるのか、あるいは、キルステン・ダンストはフィリピン映画を見たことがあるのか、あるいはドナルド・サザーランドはルーマニア映画を見たことがあるのか、など、意地悪な考え方をしようと思えばいくらでもできます。ルーマニア映画のこの10年の動きの中でムンジウの最新作をどう位置付けるか、あるいは、ドランの新作の出来は近作と比べてどうなのか、などという議論はそもそも起こり得ないのがカンヌの審査でしょう。
そうではなく、1本毎の作品の出来を絶対評価で審査し、ほかのコンペの20本と比べてどうなのか、という議論をすることがカンヌの審査員の顔ぶれから想像される審査過程であり、それは否定されるべきものでは全く無く、プロが自分の経験に即して目の前の映画の優劣を判断する、というプロセスはひとつのあり方ではあります。
なので、その結果どのような作品が受賞しようが、本来何ら文句を言う性質のものではないでしょう。コンペの結果というのは、そういうものなのだから。
でも、それは分かっているけれども、今年のカンヌのコンペでは受賞しなかった作品に優れたものが多かったので、それらの作品が「受賞しなかった作品」として、受賞作よりも劣後した扱いを受けてしまう危険性をとても憂慮してしまいます。なので、そんなことが無いように(と僕がここで吠えたところであまり役には立ちませんが)、改めて受賞には至らなかったいくつかの作品の良さを大声で主張しておきたいと思います。
まずは、何と言ってもドイツのマーレン・アーデ監督による『Toni Erdmann』(写真/「カンヌブログDay7」参照)。この作品が無冠に終わったことは、衝撃と言っていいほどの驚きをもたらしました。今年のカンヌを席巻したのは、間違いなく本作であると断言できます。映画祭前半に上映され、「『Toni Erdmann』見た?」が人とすれ違うときの合言葉になっていたほどで、見た人全員がほぼ絶賛状態でした。映画祭終盤になると、さすがに「確かに良かったけれど、評判が盛り上がり過ぎて、実際に見たらそこまでではなかった」という意見も聞かれるようにはなりましたが、それでも面白さを否定する人は皆無でした。
固い内容の作品が並ぶコンペの中で、数少ない爆笑必至の作品であったこと、しかしただのコメディーではなく、父と娘の関係回復の物語という確固たるドラマの軸を持っていたこと、そしてビジネスで成功するプレッシャーに押しつぶされようとしている娘の姿にはドイツの現在の社会が投影され、道化的な父親に翻弄される娘に人間回帰のメッセージが託されるという、巧みな作品であったことが特筆されます。さらに、常連監督が居並ぶコンペのラインアップにおいて、ドイツから久々に大物感が漂う新しい存在が台頭してきた、という喜びがあったことも無視できません。
今年のコンペの常連監督たちは、いずれも水準作を揃えてきたけれども、自己最高を更新した監督はいなかった、というのが僕の感じたところです。『アデル』のケシシュ(’13年パルムドール)や、『冬の轍』のジェイラン(’14年パルムドール)のときのように、実力派監督による、これぞ! という決定打は出てきませんでした。順番から行くと(というのも外野的な見方ですが)、ファルハディがいいタイミングかなという予想はありましたが、『The Salesman』は、面白かったものの、『別離』のインパクトを超えるほどではなく、ムンジウの『The Graduation』も過去作を凌駕はしていなかった。
それだけに『Toni Erdmann』の新鮮さは魅力的だったし、カンヌのコンペは新人発掘の場ではないとはいえ、常連監督たちを押しのける場所を用意してあげたかった。今年のカンヌで『Toni Erdmann』を見た、審査員以外の全員が落胆していると思います。日本公開が実現した暁には、堂々と「カンヌ映画祭の話題を独占した作品」とアピールしてもらいたい。間違いなく、2016年カンヌ映画祭の幻の(あるいは実質的な)パルムドール作品と言っていいはずです。
いや、ここまでダラダラと、物分りが良さそうに書いてきましたが、パルムドールは無理としても、いくらなんでも無冠はねーだろ、といまでも結構本気で腹が立ってます。2012年のカンヌが、レオス・カラックス『ホーリー・モーターズ』に賞をあげなかった年として記憶されているように、2016年のカンヌはマーレン・アーデの『Toni Erdmann』を無視した年として我々の記憶に刻まれるだろう…。
はい、しつこいですね。いい加減にします。
常連監督の中では、ジム・ジャームッシュの『Paterson』が事前の想像を越えた存在感を発揮しました。僕の偏愛かと思いきや、意見を同じくする人がかなり多く、これはひょっとして可能性があるのではないかと、クロージングに向かって僕の気持ちは密かに盛り上がった…。しかし、無冠。
静かで落ち着いた作風なだけに、ジャームッシュは枯れてしまったとの感想を持った人もいたようだけれど、僕は彼が「がなり立てるばかりが映画ではないぞ」と言っているようで、深化したというか、極意を悟った境地の美しさを見る思いでした。押してばかりの映画が揃うコンペの中で、引いた魅力を備えた唯一の作品であり、それだけに際立っていた。『Paterson』が持つ引きの魅力を無視することは、映画表現の可能性を狭めることにもなり、将来の映画のあり方にダメージを与えるほどだと思うのだけれど、審査員はどう思ったのだろうか…。
常連監督ではなく、非カンヌ的大物だっただけに事前に話題になったのが、ポール・ヴァーホーヴェン監督の参加。期待と不安が入り混じった思いで見た『Elle』は、ヴァーホーヴェンのスケール感が存分に発揮された傑作で、主演のイザベル・ユペールは、トラウマと変態性と常識人の要素を無表情の仮面の下に隠し、見る者を吹き飛ばす勢いでキャリアの集大成的で圧倒的な演技を見せました。しかし、無冠。
今年の全体的な特徴のひとつに、女性が映画の中心となる作品が多かったことがあげられます。コンペ21本中、女性が大主役であった作品は、『Toni Erdmann』(上述のドイツ映画で娘役が主役のひとり)、『Julieta』(アルモドバル監督でアドリアーナ・ウガルテ主演)、『American Honey』(アンドレア・アーノルド作品でティーン少女が主役)、『Personal Shopper』(アサイアス監督でクリステン・スチュワート主演)、『The Unknown Girl』(ダルデンヌ兄弟監督でアデル・ハネル主演)、『From The Land of the Moon』(ニコール・ガルシア監督でマリオン・コティアール主演)、『Aquarius』(ブラジル映画で中年女性がヒロイン)、『Ma’ Rosa』(フィリピン映画で中年女性がヒロイン)、『The Handmaiden』(パク・チャヌク監督でタブル・ヒロイン)、『The Last Face』(ショーン・ペン監督でシャーリーズ・セロン主演)、『Elle』(上述のイザベル・ユペール主演)、『The Neon Demon』(ニコラス・ウェンディン・レフン監督でエル・ファニング主演)、と実に12本あり、例年の傾向を調べていないので単純に言いきれないですが、これはなかなか多いのではないでしょうか。
それぞれ魅力的な女優たちが様々な女性の生き様を演じ、こうやって書きながら思い出しても幸せな気分になれるのですが、映画の完成度に女優が高いレベルで貢献している作品としては『Toni Erdman』、『Aquarius』、そして『Elle』の3本が突出していました。その中でも圧巻のプロの仕事を見せたユペールには、『ピアニスト』以来15年振りの女優賞がふさわしかったと強く思います。実際に受賞したのは『Ma’ Rosa』のジャクリン・ホセで、彼女の魅力も僕は全く否定する立場ではありませんが、ユペールが到達したレベルはやはり次元が違うと言わざるを得ません。
女優が男優の相手役や、添え物ではなく、堂々と活躍する作品を見るのはとても気分が良くなりますね。超激戦となった今年の女優賞争いでしたが、この傾向に何か背景があるのかどうか。来年も注目したいところです。
同じく女優賞を逃した『Aquarius』ですが、ブラジルの港湾都市のレシフェを舞台に、住居の買い占めに抵抗する中年女性の物語で、背筋のしゃんと伸びたヒロインの生き様が魅力的であると同時に、資本と搾取の構図を批判する社会派の側面を備えた秀作でした。クレベール・メンドンツァ・フィリョ監督は、建物とスペースを独特な視点で切り取るフレーミングが特徴で、そのスペーシーな画面に音楽を重ねることでスケール感を出すスタイルが前作から共通しています。独自の作家性が感じられる監督なだけに、将来が期待され、無冠に終わったことはここでも非常に残念であると嘆くばかりです。
上記以外の非受賞作では、ブリューノ・デュモン監督が新境地を展開する『Slack Bay』や、ますます自由なセクシャリティ描写と特異なストーリー・テリングが際立つアラン・ギロディー監督『Staying Vertical』も、今年の忘れてはいけない重要作としてメンションしておく必要があります。また、ジェフ・ニコルズの『Loving』は、ストレートな感動作なだけに、個性派ぞろいの作品群の中では埋もれがちだったけれども、主演のジョエル・エドガートンの絶妙な演技とともに鮮やかな印象を残したことは特筆に値します。
そして、ルーマニアのクリスティ・プイユ監督『Sieranevada』。ドキュ的自然派カメラの長廻しと、細かい繋ぎを独自の「ルーマニア的」テンポで組み合わせて、迫真のリアリズムを作り出す。そして、多くの人物を自在に出入りさせ、計算され尽くしたカオスを作り出し、狭いアパートの中で親族という巨大な小宇宙を見事に描いて見せる傑作でした。オルタナティブな映画表現のひとつの究極の形であり、監督賞を受賞した同胞のムンジウに劣ることは全く無く、ルーマニアの異才としてプイユは存分に力量を発揮しています。これもまた、無冠が惜しまれる作品でした。
というわけで、今年のコンペで受賞した作品はめでたいけれど、受賞していない作品にこそ重要作がたくさんあるよ、という総括でした。
【「ある視点」部門について】
「ある視点」部門は、深田晃司監督『淵に立つ』の審査員賞(2等賞)受賞で一気に盛り上がったわけですが、念のため以下に受賞結果を記しておきます。
・作品賞(1等賞):『The Happiest Day in the Life of Olli Maki』(フィンランド/ジュホ・クオスマネン監督)
・審査員賞(2等賞):『淵に立つ』(日本/深田晃司監督)
・監督賞:マット・ロス監督『Captain Fantastic』(米)
・脚本賞:『The Stopover』(フランス/デルフィーヌ&ミュリエル・クーラン監督)
・特別賞:『レッドタートル ある島の物語』(仏日/ マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督)
作品のストレートな「面白さ」という点では、『淵に立つ』の方が『The Happiest…』に勝っていると思いますが、後者には野心的な遊びも見られ、審査員はその可能性を買ったのかもしれません。両作品を巡って4時間議論したそうなので、もはや同率1位と言っていいくらいの評価だったのでしょう。
「ある視点」部門のその他の作品を見ると、映画の語り口を工夫して、味はあるのだけれど小さくまとまってしまった作品や、着眼点は面白いけれど仕上がりは普通、という作品が目立ったかもしれません。
その中で、エジプト革命後の混乱を警察の搬送トラックの中だけで描いた意欲作『Clash』、キリスト教の聖書原理主義に目覚めた高校生が暴走するロシアの『The Student』、大都市テヘランで問題に直面する家族のドラマを緊迫感交えて描いたイランの『Inversion』あたりが、賞の有力な対抗馬ではなかったかと想像します。これらの作品は僕も大いに推したいところです。
『淵に立つ』は上位に食い込むレベルの作品であったことが、他作品を見ていく過程で分かってきましたが、若手の日本人監督が受賞に至ったポイントは何だろうと、つい考えてしまいます。ひとつ単純な比較として、上記の『Clash』、『The Student』、『Inversion』はいずれも特殊な状況をゴリゴリと押してくるタイプであり(特に前者2作はかなり激しい)、日常の延長線上にあるホームドラマ・心理スリラーという佇まいの『淵に立つ』が受け入れられやすかったのかもしれない、という点はあると思います。
また、平穏な日常生活に闖入者が現われるという『淵に立つ』の設定は、深田監督が2010年に作った『歓待』にも共通していますが(それもそのはずで、深田監督はもともと『淵に立つ』の構想を長年抱いていたものの、資金が足りず短編企画とした後、やはり長編でないと展開しにくいということで短編脚本を改めて長編映画化したのが『歓待』になった、という変遷があるらしい)、「闖入者もの」は映画好きの心に訴える古典的ジャンルであり、深田晃司がヌーヴェル・ヴァーグ的シネフィル監督の系列に位置することが、海外の目の肥えた観客には伝わる。
ところで、「ある視点」部門の審査員のひとりであるリューベン・オストルンド監督は、『Play』(’11)や『フレンチアルプスで起きたこと』(‘14)を作ったスウェーデンの鬼才でありますが、人が不快に思う心理のツボを絶妙に突いてくるセンスに関しては、当代随一の才能の持ち主です。受容と非受容をめぐる心理の動きを好んで描く点で、深田監督と共通していると言えます。
で、深田監督本人から聞いたわけではないので、僕の純粋な想像でしかないですが、そのリューベン・オストルンド監督が『淵に立つ』を気に行ったであろうことは間違いない。浅野さんと古舘さんと筒井さんが演じたキャラクターの関係性を、リューベンが気に入らないはずがない。もうこれは賭けてもいいくらいです。
なので、『淵に立つ』が「ある視点」に選ばれた年に、リューベン・オストルンド監督が審査員にいたということは、とても幸運であったということが言えると思います。コンペに関して上述したように、作品の受賞の行方は、審査員の相性との運に左右されがちです。映画の神は、審査員にリューベンを配することで『淵に立つ』に味方したのでした。
もうひとつ重要であると思われるのは、『淵に立つ』が、「罪と罰」という西欧的テーマを持ち、キリスト教の存在にも触れていることです。我々の罪とどう立ち向かうか、という映画が投げかける根源的問いが、欧米人が中心となる審査員(や観客)に受け入れられやすかったであろうという点は、指摘しておいた方がいいと思います。もちろん、キリスト教を題材にしたらすぐに欧米で受け入れられるほど単純なことではなく、何年間もかけて練り上げられた脚本の土台があってこその感情の共有であることは、言うまでもありません。
ということを考えて行くと、『淵に立つ』の受賞はかなり必然的なものであった気がしてきますね。本当に、おめでとうございます!
僕は未見のままで残念でしたが、同僚は監督賞を受賞したヴィゴ・モーテンセン主演の『Captain Fantastic』を絶賛しており、これは日本公開を期待したいところです(残念ながら僕は情報が無いのですが)。
【「監督週間」「批評家週間」について】
「監督週間」は結局あまり見られなかったので、個人的には悔いが残るところです。フランスの『Divines』という作品が、カンヌ映画祭全部門を通じての「カメラドール(新人賞)」を受賞しています。授賞式で登壇した監督が興奮してFワード連発しながら延々と叫び続けたことに会場が引いてしまい、いささか痛い場になってしまいましたが、映画に罪はない。でもちょっとあの態度はどうかと本当に思うけど…。
部門のオープニングだったベロッキオの『Sweet Dreams』、パブロ・ラライン監督『Neruda』、ホドロフスキーの『Endless Poetry』などが、順調に評判が高かったかな。
「批評家週間」の長編コンペ部門で作品賞を受賞したのが、モロッコの山岳地帯を舞台にした『Mimosas』という作品。僕は未見なので、これから追いかけてみるつもり。2等賞のトルコ映画『Album』を僕は評価しなかったけれど、同僚は気に入っており、結果受賞をしたのでやはり映画の評価は難しい。次点のイスラエル映画『One Week and a Day』は、前半が辛かったものの、後半一気に好転する感動作で、納得。これまた見逃してしまったカンボジア系フランス人のダヴィ・チュウ監督『Diamond Island』も好評で、嬉しい結果でした。
「批評家週間」で何と言っても気に入ったのが、フランスの(人)肉食映画『Raw』で、気持ち悪さと笑いとが高い次元で達成された傑作でした(「カンヌブログDay5」参照)!この監督が相当のセンスの持ち主であることは疑いようがないので、近々天下を取るような気さえします。何も受賞しなかったのが不思議なくらいで、あまりにも血みどろなので審査員は敬遠したのかな。カンヌはそんな保守的な場ではないはずなのだけど。ともかく、今後の展開が楽しみです。
さて、そろそろいい加減にします。長々と総括的に書いてしまいましたが、なんだかんだで今年も充実のカンヌでした。賞の結果にとらわれ過ぎず(でも深田監督の受賞は喜びつつ)、優れた作品の良さがこれから日本でも伝わっていくことを願うばかりです。