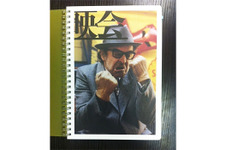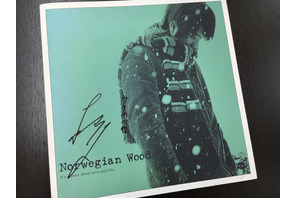【MOVIEブログ】コンペ作品紹介(2/3)
コンペ作品紹介の第2弾です。5作品行きます。相変わらず長文で失礼します。
最新ニュース
スクープ
〇『1001グラム』 (ノルウェー)
ベント・ハーメルという監督の名前は、映画ファンの間には浸透しているでしょう。『キッチン・ストーリー』(03)や『ホルテンさんのはじめての冒険』(07)を始めとして、監督作の多くが日本でも公開されているし、ノルウェーを代表する監督のひとりです。特徴は、平凡な小市民が懸命に生きる姿から見えてくる「おかしみ」を、センス良く、そして暖かく描くことにあると言えますが、ウェルメイドでハートウォーミング(少し苦めの時もある?)な作品を作る達人という印象があります。
本作は、そんなベント・ハーメルの世界が全開、いや、さらに洗練された形で展開する、鮮やかな出来栄えの作品です。東京国際映画祭のコンペティションを見たことが無いのだが何から見ればいいのだろう、という方には本作がお勧めですし、デートでもOK、女性どうしで見に行くもOK。そして熱心な映画ファンであれば、ハーメルの世界観の見事な構築ぶりに快感を覚えずにはいられないはずです。
まず、設定が面白い。パリに、世界の重さの基準となる「1キログラム」の重りが保管されている(事実)。そして、各国にも、自国の基準となる「1キロの重り」があって、本作のヒロインは、その重りが保管されている測量研究所に勤める研究者です。年に1回の学会で、自国の1キロを確認すべく、各国の研究員がパリに集結するのですが、ノルウェーから毎年出向いていた父に代わり、ヒロインが初めてパリに赴くことになるが…、という物語。
30代のヒロインの「成長」を描く物語ですが、物理的な1キログラムという物質をモチーフにしながら、様々な「心の重み」を経験していく、という仕掛けが、もう何とも巧みで上手い。
画面作りにとても特徴があって、「北欧デザインのような」という表現を僕も既に色々なところで使ってしまっているけれど、とにかく、シンプルで機能的で美しいのです。一見、シャープで、寒色が目立つクールな見栄えなのだけれど、そこで展開する物語が暖かいので、とても居心地がいい。ヒロインの心の推移の描き方もスムーズで、ほのかなユーモアのセンスも抜群だし、無駄なシーンがひとつもない。隅々まで演出の行き届いた完璧な作品、と言っても言い過ぎとは思えないほど、完成度の高い作品だと僕は思っています
誰が見ても満足できる作品の代表格が、『1001グラム』です。
〇『マイティ・エンジェル』 (ポーランド/写真)
一方、観る人によってはかなり評価が分かれるであろう作品が、本作です。こんなことを言ったら監督に叱られそうだけど、監督も万人受けする作品を作っていないことは自覚の上だろうから、構わないはず。ともかく、コンペ15作品のうち、もっとも歯ごたえがあり、もっともガツンとくる強度を持ち、もっとも監督の個性が強烈な形でほとばしるハードな作品です。
監督のヴォイテク・スマルゾフスキは、2009年に『ダーク・ハウス/暗い家』という作品でトウキョウのコンペに参加しています。『ダーク・ハウス/暗い家』は陰惨な殺人事件の起きた家を巡り、現場検証を行う現在と、事件発生時の過去を上手くつなげ、重量感のある鈍い迫力に満ちた怪作であるとともに、映像センスに目を見張る美しい作品でもありました。
本作の主人公は、アルコール依存症の作家。彼が、自分の経験を語っていく形で映画が進みます。ウォッカを絶え間なく飲み続け、路上に倒れ込んでは、駆けつけた救急隊員によってリハビリ施設に運び込まれる主人公のどん底の姿が、露悪的とも言える生々しいタッチで描かれます。そして、度重なる収容を通じて知り合った他の患者たちのエピソードも、短編映画のように挿入され、まさに悪夢のような体験のタピストリーが織られていきます。
そんなしんどい映画見たくないよ!と思ったそこの貴方。ちょっとだけ待って下さい!この作品には、確かにリアリズムに徹した厳しい描写が溢れていますが、そこで観客を突き放すのではなく、逆に観る者を引きこんでいく不思議な吸引力が備わっているのです。これは、本当に不思議で、不快感はあるにはあるのだけれど、目を背けたいどころか、目が釘付けになってしまう魔法を持っているかのようです。
その魔法こそ、監督の技量に違いありません。映像の魔術を知り尽くした監督が、細かい編集技術を駆使し、物語の時制を激しく入れ替えたり、反復を利用したりして、観る者を劇中の人物と同様の混乱と酩酊に誘っていきます。果たして自分はいつの時を過ごしているのか。今、自分はどのくらい正常なのか…。
必ずしもアルコールの持つ危険性を告発する内容ではなく、アルコールによって崖っぷちに追い詰められた人々のドラマの中に、人間の本質を見出だそうとする作品です。映画はあくまで人間の感情に寄り添い、人間の心の闇を見つめようとします。闇の先に希望はあるか。そして、愛は?
本作を既に見ている知人が、「このような作品に出会うことが、まさに映画祭の醍醐味である」と断言していました。確かに、日常的に劇場でお目にかかれるタイプの作品ではないでしょう。ただ、その分、個性が突出しており、監督のスタイルの強烈さはコンペでも屈指のものです。スマルゾフスキ監督は、ポーランドを代表する個性派監督として、今後一層独自の地位を確立していくでしょう。
真の意味で映画祭を「体験」するなら、『マイティ・エンジェル』!
〇『ナバット』 (アゼルバイジャン)
また「じっくり系」に針を戻します。本作は、山間の村でひとり取り残された老女の姿を、じっくりと、しみじみと、厳しく、そして優しく見つめていく、映画的な美しさに溢れた作品です。では「映画的な美しさ」とはなんだ、ということなのですが、それは余計なセリフによる冗長な説明を排し、映像の力で物語の本質を描いていく、映画に特有な手法を活かした美しさ、と言い換えることが出来るかもしれません。
実際に、ファーストシーンを見た時に、ほぼ僕の心は決まっていました。荒涼たる景色が広がる中、遠くの丘の上から、女性らしき人物が大きな容器を両腕に抱え、画面に向かって歩いてくる。一瞬、谷に姿が隠れるものの、また現われてカメラの前を通り、谷向こうの村に向かっていく。これがワンショット。冒頭から、思わず溜息が出るショットです。
90年代初頭、ソ連崩壊に伴う混乱に揺れる西アジア地域を舞台にしています。監督が実際に当時見聞きしたエピソードを映画化したものとのことですが、戦火が近寄ってきたことで住民が避難してしまった村に、ひとり残ったナバットという名の老女の姿を描いていきます。
第一の見どころは、繰り返しになりますが、何よりも雄弁なキャメラです。ダイナミックにして繊細で、美しい。綿密なプランに基づいていることは確かですが、しかし時折、画面の中で奇跡的な動きが起きることがあります。演出を超えた何かが起きているという興奮に、胸のざわめきを抑えることが難しい。そして映像は、物語を語るに雄弁であると同時に、老女の感情も繊細に捉えていきます。ナバットは言葉少ない分、その一挙一動が彼女の感情を表し、その様子をキャメラが緩急の効いたリズムで掬っていく。この演出が心に染みてくるようで、実に上手い。
いや、映像が雄弁とか、演出が上手いとか、何やら通ぶった感想はいい加減にした方がいいですね。本作は、何よりも戦地に息子を送った母の悲痛な思いを映画化した感動作であり、ナバットを取り巻く自然や動物たちも一体となった、生命への賛歌です。真っ白な心で向かい合うと、切なくも暖かい感動で胸を満たしてくれる作品です。
そして、もはや自明かもしれませんが、第二の見どころはナバット役の女優さんです。ファテメ・モタメダリアさんはイランを代表する女優のひとりであり、2年前の東京フィルメックスの審査員を務めるなど、日本にも縁のある存在です(今年の釜山映画祭の審査員も担当なさっています)。厳しい自然環境の中で生き延びるタフな妻と、悲しみを胸の奥深くにしまい込んだ母親と、ふたつの側面を持つ女性を抑制の効いた演技で抜群に表現し、主演女優賞候補に挙がることは間違いないでしょう。
主演女優はイラン人ですが、アゼルバイジャン映画です。言語はアゼルバイジャン語だとのことですが、イランの人もある程度使えると聞きました。また、この作品の試写を、トルコ語の通訳の方と見たのですが、トルコ語とも近いようで、3~4割は理解できると通訳の方は仰ってました。実際、アゼルバイジャン映画がトウキョウで上映されるのは珍しい一方で、トルコ映画は毎年のように選定しており、トルコ映画の充実した状況がアゼルバイジャンにも影響を与えているのではないかと想像したくなります。地域の映画事情など、監督に直接聞いてみるのが楽しみです。
今年のコンペの「じっくり系」代表、『ナバット』をお見逃しなく!
〇『ロス・ホンゴス』 (コロンビア)
舞台を南北アメリカ大陸に移して、南米コロンビアの作品です。南米は相変わらず面白くて、という言い方はあまりにも乱暴ですね。メキシコ、チリ、アルゼンチン、などは毎年順調に良作が連発されていますし、コロンビアもここ数年勢いを増している印象があります。ブラジルももちろんいい。現在東京で開催中のラテン・ビート映画祭も絶好調ですが、カンヌを始めとする世界の有力映画祭を、近年のラテン系の映画は席巻していると言っても過言ではないです。
さて、本作は青春映画です。アフリカ系の黒人の青年と、ヒスパニック系の白人の青年が親友どうしで、前者はスケボー、後者は自転車で、コロンビアの南西に位置する中規模都市カリのストリートを滑走します。ふたりの共通の趣味はグラフィティ・アートで、街のはずれの大きな壁面にメッセージを込めたペインティングをゲリラで施す大規模なイベントへの参加を軸に、彼らの成長を追っていくのが本作の物語です。
この作品が凡百のストリートものと一線を画していると僕が感じているのは、文化が人間の成長に果たす重要性が強調されているのと同時に、そこに政治や宗教といった要素が自然に入り込んできて、懐の深い作品に仕上がっているという点です。主人公たちに馴染みのある若者カルチャーだけでなく、祖母の世代の人間が親しむ音楽も主要な位置を占めており、青年たちは旧世代との接触を厭わないことで、知らないうちに自らを高めていくのですが、その展開に何とも言えず気持ちが良くなります。
そう、本作は本当に気持ちがいい。何よりも、音楽がサイコー!風通しがよく、ユーモアと優しさに溢れ、ポップなセンスも実にナイス。しかし問題意識がはっきりしているので、甘酸っぱい恋に終始するようなヤワな話ではなく、青春期から大人への脱皮のきっかけとなる決定的な瞬間を、スナップショットで捉えたような鮮やかな作品です。
オスカル・ルイズ・ナビア監督は、2010年の処女長編『Crab Trap』が、同年のベルリン映画祭のFIPRESCI賞(国際批評家連盟賞)を受賞しており、僕もその時に見て以来、気になっていた監督でした。『Crab Trap』はもっと抽象的で、よりドキュメンタリー色も強かったと記憶しているけれども、本作ではドラマとしての骨格をしっかりとさせながら、自由なタッチのドキュメンタリー風味は残っており、その為なのか、コロンビアの「現在の空気」がリアルに感じ取れるような雰囲気に満ち溢れています。
伸び盛りのラテンの注目株監督による、今年のコンペにおける爽やかさ度1位が『ロス・ホンゴス』です。
〇『神様なんかくそくらえ』 (アメリカ)
「じっくり」と「さわやか」が続いた後に、またまた「激しい系」に戻ります。『神様なんかくそくらえ』は、NYマンハッタンのストリートにおいて、ドラッグを求めてさまよう若いジャンキーたちの生態を生々しく描いたもので、情け容赦の無い、激しくも乾いたリアリズムの世界です。僕は先日の記者会見で、本作のことを「かつてのハーモニー・コリンから情緒を取っ払った世界」と説明したのですが、ちょっと暴走しましたね。どれだけ伝わっただろうか…。
監督は、ジョシュとベンのサフディ兄弟で、アメリカのインディペンデントシーンでは有名な存在です。2008年の長編デビュー作品『The Pleasure of Being Robbed』がカンヌ映画祭の監督週間で上映され、そのセンスの良さが評判を呼び、僕も同作以来、動向を追っていた監督たちでした。
5年振りのフィクション長編となる本作は、NYを舞台にリアルな若者像を描くという以前までの路線は継続していたものの、今まで見られたセンスの良いキュートさは影を潜め、激しいリアリズムが支配することに驚かされます。2013年に初のドキュメンタリー映画を監督していることが、彼らをよりリアリズムに傾倒させるきっかけになったというのは僕の邪推に過ぎないとしても、どこかで舵を切らせるタイミングがあったのかもしれません。
その「どこかのタイミング」というのが、アリエル・ホームズとの出会いだったのかもしれません。というのも、『神様なんかくそくらえ』の最大の特徴は、本作がヒロインを演じるアリエル・ホームズの実体験をベースにした物語であることなのです。つまり、アリエル・ホームズはもともとストリートでジャンキー生活を送っていたのが、その体験談を兄弟監督が聞き、脚本に起こし、映画化し、そこでアリエルは自分の役を演じてしまったのです。ただでさえシビアな状況を描く中で、彼女の演技はさすがに迫真そのものであり、本作が並々ならぬリアリズムを備えているのはその為であることが分かります。
僕が刺激を受けたのは、本作が描くジャンキー青年たちの、希望もない代わりに絶望もないニュートラルな姿だったのですが、それは観る人によって感想が全く異なるかもしれません。この作品を見て、とにかく大勢の人と話をしたいのだけど、今のところ同僚ひとりしかいないので、物足りないことこの上ない。早く映画祭で上映されて、多くの人と意見交換がしたい!
不協和音を駆使したスコアが響く不穏な冒頭が鮮烈で、やはり只者ではないサフディ兄弟のセンスが直ちに炸裂します。ノーフューチャーなホワイトトラッシュ最新版であり、どん底から見たニューヨークの風景の「今」であり、絶望的な愛の物語でもあります。いや、これが愛なのか、よく分からないのだけれど、ある種の愛の形であるのは、どうやら間違いない。それがどんな形なのかは、これもやはり上映後の議論のためにとっておくことにしましょう。
今後が一層期待されるサフディ兄弟を、このタイミングで日本に紹介できることにとても興奮します。ふたりの兄弟監督、主演のアリエル・ホームズ、そして共演のケイレブ・ランドリー・ジョーンズ(『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』『ビザンチウム』等)の、合わせて4人で来日予定です。アメリカン・インディーズの最前線を、どうぞ直接目撃して下さい。