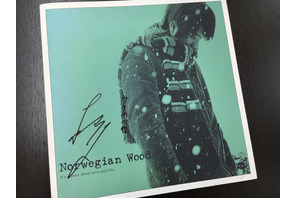■『Never Rarely Sometimes Always』(エリザ・ヒットマン監督/アメリカ)

ニューヨーク出身のエリザ・ヒットマン監督は長編1作目『It Felt Like Love』(13)でナイーヴな14歳の少女の内面を瑞々しく描き、2作目『Beach Rats』ではゲイという自らのセクシャリティとうまく折り合いが付けられないハンサムな青年の心情を繊細に描いていました。2本とも良作でしたが、特に2作目はナチュラルなリアリズムに溢れ、1作目からの進化が確実に感じられて監督の才能に期待が募ることになりました。
ロッテルダムやサンダンスなどの有名映画祭に参加してきたヒットマン監督ですが、長編3作目となる本作で初のベルリンコンペです。才能が順調に伸びていく過程に立ち会う喜びに興奮します。
新作は、2人のティーンの少女が望まない妊娠に手を貸してくれる医師を求め、地元ペンシルヴァニアからニューヨークに向かう旅を描くドラマであるようです。この設定自体に新鮮味はあまり無いかもしれませんが、監督の過去2作を見て思うのは、ヒットマン監督は普遍的なドラマの中に新たな視点を見出し、繊細で良質なアート作品に仕立て上げるセンスと技術に長けているのだということです。
自らの生活と地続きの世界を描いている監督でもあるという印象があり、もしかしたら数年のうちにノア・バームバックやグレタ・ガーウィグのような存在になるかもしれません。注目して追いましょう。
■『Days』(ツァイ・ミンリャン監督/台湾)
ええー? ツァイ・ミンリャン!? と会食中に同僚からLINEを受け取った僕は叫んでしまいました。それほど、近年のツァイ・ミンリャンは実験映画に近いというか、「あっち側に行ってしまった人」という印象を僕は抱いていました。『郊遊<ピクニック>』(13)で男が壁を10分以上凝視し続けるのはまだよかったとして、「歩くシリーズ」で僧侶に扮したリー・カーションが超ゆっくりと歩く様を延々と見ていると、ちょっともはやどう反応していいものか、僕は戸惑いが先行していたことを白状せねばなりません。
いや、実験映画が悪いというつもりは全くなくて、ツァイ・ミンリャンの関心が通常映画から別のフォルムに移り、映画祭のコンペティションを意識するような創作活動から離れていたと勝手に思っていたのでした。実際、ロンドンのテート・モダンで上映会が行われており、ツァイ・ミンリャンが映画監督から現代アートのアーティストとなったことはあながち間違いではないかもしれません(そのふたつを区別する必要があるのかという議論は当然あるとして)。
もちろん、ツァイ・ミンリャンがベルリンのコンペに入っていることにとてもエキサイトしています。アジアからホン・サンスとリティ・パンとツァイ・ミンリャンなんて、最高です。しかし、本作の内容については調べきれませんでした。中国語サイトを探したら何か見つかるでしょうか(僕は中国語が分からないので…)。
近年は、歩く僧侶シリーズなどの現代アート系の作品や、アートとドキュメンタリーを融合した短編を中心にした創作を続けていましたが(野上照代さんを撮影した短編もある)、『Days』は長編であろうとは予想するものの長さの情報もなく、物語があるドラマなのか、現代アートなのか、どういうものなのか分かりません。あ、リー・カーションは出ます、もちろん。ともかく、心して上映日を待ちましょう。
■『The Roads Not Taken』(サリー・ポッター監督/イギリス)

90年代に『オルランド』(92)や『タンゴ・レッスン』(97)で映画ファンを興奮させたサリー・ポッター監督、健在です。前作『The Party』(17)もベルリンコンペで上映されていて、手練れの役者たちによる軽妙な大人の会話劇が楽しめる上質な娯楽作でありました。
今作は、精神的に混乱している父親と、彼の面倒を見る娘の物語で、ふたりはニューヨークで休暇を過ごすことにするものの、父の頭の中には、選ばれることの無かったいくつもの人生が存在しており、そして娘も自分自身の人生を獲得しなければならなかった…、という感じの物語。
父親役にハビエル・バルデム、娘役にエル・ファニングという、今年のベルリンコンペの中で最強のキャストを誇り、映画祭の華やかな話題の中心のひとつになるでしょう。
■『My Little Sister』(ステファニー・シュア&ヴェロニク・レイモン監督/スイス)

ステファニー・シュアとヴェロニク・レイモンの監督コンビは幼少期からの知り合いだとのことで、共同で演劇の創作などを経たのち、2010年に初長編劇映画を手がけ、ロカルノ映画祭でプレミアされています。残念ながら僕は未見。その後テレビシリーズやドキュメンタリーを手がけ、本作が2本目の長編劇映画のようです。
本作も情報があまりなく内容が分からないのですが、主演に『東ベルリンから来た女』(12)やドラマの「ホームランド」などでお馴染みのニーナ・ホス、そして共演に『ブルーム・オブ・イエスタディ』(16)のラース・アイディンガーと、人気のドイツ人俳優が出演することで、ベルリンの観客が大いに盛り上がるであろうことは想像に難くありません。
■『There is no Evil』(モハマド・ラスロフ監督/イラン)
モハマド・ラスロフ監督は現代イラン映画を代表するひとりであり、現政府の検閲方針に真っ向から挑む内容の作品を発表して禁固刑を言い渡され、現在も係争中のはずです(最新情報確認中)。
『Manuscripts don’t Burn』(13)はイランの検閲体制をダイレクトに告発し、『A Man of Integrity』(17)は裏社会と官僚組織の双方から圧迫を受ける男の復讐劇でしたが、いずれも情動的なドラマでなく、作家性の強い映画作りを貫いている点がラスロフの評価を高める要因でもあります。アクションの帰結となるドラマをあえて描かず、アンチ・エモーショナリズムとでも呼ぶべき省略話法に挑んでおり、主題においても表現においてもタフな芸術家であります。
ラスロフ監督はカンヌの常連ですが、ベルリンは初めての参加。おそらく、出国できず、監督のベルリン入りは叶わないのではないかと思われます。本作の招聘は硬派ベルリン映画祭の面目躍如と言えますし、僕は歯ごたえのあるラスロフの演出に再度挑めることに興奮を覚えつつ、厳粛な気持ちで上映に臨むつもりです。
■『Siberia』(アベル・フェラーラ監督/アメリカ)

アベル・フェラーラ監督新作。監督がNY出身なのでこのブログでは「アメリカ」と書きましたが、映画の正式クレジットには「イタリア/ドイツ/メキシコ」とあります。NYを舞台にした作品も多いですが、ゼロ年代から拠点をイタリアに移し、主にヨーロッパで作品を製作しています(が、もちろんアメリカでも撮影はしている)。
フランスの大統領候補と目された超大物政治家が失墜した大スキャンダルを描いた『ハニートラップ 大統領になり損ねた男』(14)や、パゾリーニの最後の日々を描いた『Pasolini』(14)など、選ぶ題材がいささかあざといなあと思わないではないのですが、もともとハッタリが本分の監督でもあるので、これも個性ということですね。
新作では、『ニューローズホテル』(98)以来、組むのが6作目となるウィレム・デフォーを主演に起用しています。凍ったツンドラ地帯で、魂の折れた男が一人で暮らしている。孤独の中に男は平穏を見つけることができず、夢や記憶や想像の世界に没頭していく…、という物語。
「夢の言語の探索」を描く本作は、ユングの「赤の書」からインスパイアされているようです。僕は同書を未読なのでウィキペディアに頼ってみると、「赤の書」は第一次大戦下において精神的に不安定となったユングが、自らの悪夢を綴ったものであるとのこと。なるほど。
昨年カンヌ映画祭の「スペシャル・スクリーニング」でプレミア上映された前作『Tommaso』(19)は、デフォー扮するローマ在住のアメリカ人映画監督が嫉妬と薬物に苦しみ、夢と現実の間をもがくという内容でした。新作も監督の分身たるデフォーが主演、そしてテーマが夢となると、前作の延長戦上にあるような、フェラーラ監督が自らの内なる悪魔と闘うという内容になっているのかもしれません。
■『All the Dead Ones』(カエタノ・ゴタルド&マルコ・デュトラ監督/ブラジル)

2010年代のブラジルではホラー・テイスト、あるいはスピリチュアル・テイストを含むアート映画が一大潮流となり、その一端を東京国際映画祭でも紹介してきました。2016年の東京のコンペで上映した『空の沈黙』のマルコ・デュトラ監督は、処女長編『Hard Labor』(11)がカンヌ「ある視点」で上映され、『狼チャイルド』(17)は見事ロカルノ映画祭で審査員賞を受賞しています。
そして、『空の沈黙』を東京で上映した際に来日してくれた、共同脚本のカエタノ・ゴタルドさんが、デュトラ監督の新作で共同監督クレジット、しかもその作品がベルリンコンペ入りしているとなると、他人事とは思えない嬉しさを覚える1本です。
新作の舞台は、歴史的に過渡期にある19世紀末のブラジルで、奴隷制が廃止され、共和国が始まらんとする時期。ひとつの家族の3人の女性を巡る物語とのことで、死、病気、そしてオブセッションが家族を覆っていく様が語られるようです。マルコたちの映画は、驚かせようという商業ホラーとは対極に位置し、ホラー・テイストによって人間の業をあぶりだそうとする心理ドラマであり、そこにオリジナルなビジュアルが展開されるという極めて新鮮な映画体験が約束されています。僕は本当に楽しみにする1本です。
■『Undine』(クリスチャン・ペッツォルト監督/ドイツ)

いわゆる「ベルリン派」のひとりとしてゼロ前代のドイツ映画を牽引する存在であるペッツォルト監督は、当然ながらベルリン映画祭の常連であり、『東ベルリンから来た女』(12)では銀熊賞を受賞しています。
商業主義にアンチを突き付けたベルリン派は、多少の難解さを厭わずに新旧の世界の解釈を深める作品を発表し続けていますが、僕もペッツォルトの前作『Transit』(17)の物語の深みに2度目の鑑賞で気付いたり、昨年のベルリンコンペで銀熊(監督賞)受賞のアンゲラ・シャーネレク監督作『I Was at Home But』(19)のモザイク状の構造に魅了されたり、刺激を受け続けています。日本での紹介があまり進んでいないのが残念ですが、映画祭関係者のひとりとして、何とかしないといけないと思っています。
新作『Undine』のタイトルは主人公の名前で、ウンディーネ(オンディーヌ)という女性。本作はベルリンを舞台にした現代劇。観光ガイドとして働くウンディーネは、恋人に去られたあとにクリストフと出会い、深い交際が始まる。しかしウンディーネのある行動により、クリストフは裏切られたと感じるようになる…。
ウンディーネというのは神話上の水の精霊の名前ですね。作品のスチール写真もプールに入っている男女の姿です。愛の物語に神話がどのように絡み、いかなる世界をペッツォルトが作っているのか、ウンディーネ神話を復習してから臨んだ方が、理解が深まりそうです。
■『Hidden Away』(ジョルジョ・ディリッティ監督/イタリア)

日本ではイタリア映画祭で紹介された『いつか行くべき時が来る』(12)以来となる、ジョルジョ・ディリッティ監督の久しぶりの長編新作です。前作はアマゾンを舞台にスケールが大きく非常に美しいドラマでしたが、ディリッティ監督はドキュメンタリーとドラマを交互に手掛けており、描く主題も多岐に亘る印象がある監督です。
新作は、20世紀前半に活動したイタリアの画家、アントニオ・リガブーエの伝記映画。20歳で故国のスイスから追放されるという苛酷な過去を持ち、やがて人間社会から隔絶されたイタリアのポー川付近の森に暮らし、自然の中で動物や自然を描いて生きたという作家。前作ではジャスミン・トリンカがアマゾンに旅立ちましたが、今作ではリガブーエに扮するエリオ・ジェルマーノ(今年は2本のコンペ作に主演!)の森の日々が鮮やかに活写されるでしょう。
以上、18本の概要を予習してみました。映画祭常連のベテラン監督と、期待の若手のバランスが素晴らしくいいですね。新しいディレクターのもと、カーペットを賑わす人気俳優出演作が昨年までと比べると少し減り、アート色が例年よりさらに深まった印象はあります。硬派度が増したというか、カルロさんの気合いを感じます。1本も見逃したくありません。
ということで、ブログ上のベルリン予習はコンペだけで失礼し、次は現地から日記をアップしていけたらと思います。映画祭の動向が世界の映画のトレンドの一端を担うことがあります。是非、今年のベルリンの動向にもご注目下さい!