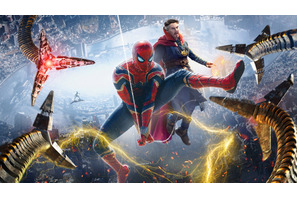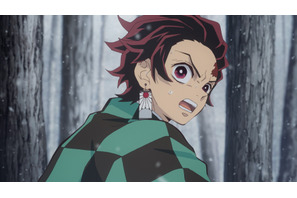ミュージカル映画ーー中でも『ラ・ラ・ランド』のようなミュージカル映画そのものにオマージュを捧げたメタ的な作品ではなく、『レ・ミゼラブル』のようなブロードウェイ・ミュージカルを映画化した本格的なミュージカル作品ーーがちょっと苦手という人は少なくないのではないか。「さっきまで普通に喋っていた人物がどうして突然歌い出したり踊り出したりするの?」というのは、それこそ昭和のテレビ番組におけるタモリを筆頭に散々語られてきたことでもある。それを言うなら、タイツ姿で高層ビルの谷間を飛び回ったり、ハンマーを手にした神が宇宙からやってきたりするのも不自然極まりない設定なわけで、映画という表現フォーマットは本質的にそうした不自然で非現実的な「見せ物」であることと分かちがたく結びついているわけだが、同じ「見せ物」でも観客によってハードルの種類が違うのは致し方ないことではある。

しかし、『イン・ザ・ハイツ』を世に送り出した劇作家リン=マニュエル・ミランダは、そんなこれまでミュージカル映画に苦手意識をもってきた人々にとって画期的な存在となるかもしれない。トニー賞はもちろんのことグラミー賞やピューリッツァー賞(戯曲部門)まで受賞した2015年初演の舞台『ハミルトン』が未上演の日本では、まだその実感を持っている人は少ないかもしれないが、実際に彼が成し遂げてきたのはミュージカルという表現フォーマットそのものの革新に他ならない。

その鍵となるのは、すばり「ラップの導入」だ。アメリカ建国の歴史を全有色人種キャストで綴った『ハミルトン』の衝撃は「ヒップホップ・ミュージカル」という呼称で世界に広がったが、そのさらに10年前にオフ・ブロードウェイで上演された舞台『イン・ザ・ハイツ』もまた、音楽的にはサルサやメレンゲやレゲトンなどのラテンミュージックが主軸となっているが、その歌唱スタイルにおいては多くの曲でラップの手法が用いられている。
どうしてラップの手法がミュージカルに革新をもたらすことになるのか? それは、ミュージカル特有の「不自然さ」を大きく緩和するからだ。政治家や活動家の優れた演説に耳を傾けている時、対立する相手を説き伏せようと言葉を捲し立てている時、あるいは好きな誰かを言葉巧みに口説こうとしている時、「なんか今の話し方、ラップみたいだな」と思ったことはないだろうか。もともと、ラップとは日常会話の延長上にある表現形式だ。ミランダの作品には、「普通に喋っていた人物が突然歌い出す」ミュージカルと違って、会話の流れからそのまま早口になって、それがリズムに乗って、ラップになっていくという展開が頻出する。

それに、ミランダ作品が映画化されるのは今回の『イン・ザ・ハイツ』が初めてだが、もしかしたら既に多くの人は、そんな「ラップ以降のミュージカル」のフィーリングを様々な作品から受け取っているのではないだろうか。例えば、一昨年公開されてロングラン・ヒットを記録した今泉力哉監督の『愛がなんだ』の終盤、岸井ゆきの演じる主人公がいきなりフリースタイルラップのスタイルで思いのたけを吐き出すシーン。あるいは、同じく一昨年公開の『ブラインドスポッティング』のクライマックスでダヴィード・ディグス演じる主人公が白人警官に言葉の力でプロテストするシーン。ダヴィード・ディグスは舞台『ハミルトン』のオリジナルキャストの一人なので、『ブラインドスポッティング』に関しては明確に「ミランダ以降」の意識をもった作品だが、他にも近年、ドラマやアニメも含め、登場人物が突然ラップするシーンに出くわした作品は一つや二つじゃない(必ずしもすべてがうまくいっているわけではないけれど)。

「ラップといえば黒人の音楽」というイメージを持っている人もいるかもしれないが、人種の坩堝ニューヨークで生まれたヒップホップ・カルチャーは、その黎明期からプエルトリカンをはじめとするラテン系のニューヨーカーも重要な役割を果たしてきた。80年代のニューヨーク(しかも、まさに『イン・ザ・ハイツ』の舞台のワシントン・ハイツ)で生まれ育ったミランダにとっても、ラテンミュージックが血と肉だとしたら、ヒップホップは空気や水のような存在だったはず。そういう意味においても、ラップの手法を導入した「より現代的で自然な表現としてのミュージカル」を切り拓いた先駆的な舞台『イン・ザ・ハイツ』が、ミランダと同じプエルトリコ系アメリカ人のアンソニー・ラモスをはじめとするラテンアメリカ系キャストと、アジア系アメリカ人のジョン・M・チュウ監督という、マルチカルチュラル(多文化)な背景を持つスタッフたちによって映画化された意義は大きい。この先、『イン・ザ・ハイツ』はミュージカル映画×ラップの持つ無限の可能性を、ハリウッドのメジャースタジオ作品として最初に世界中に解き放った映画として語り継がれていく予感がする。