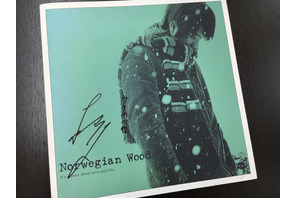『大いなる闇の日々』(カナダ/マキシム・ジルー監督)

まず北米はカナダからです。カナダは近年秀作が目立っている印象があります。いまに始まったことではありませんが、アメリカに近い、つまりハリウッドに近いということと、フランス文化圏も内包している、つまりフランスのアート系にも近い、という利点は無視できないはずです。そのハイブリッドの象徴的なスターがグザヴィエ・ドラン監督だと言えるのかもしれませんが、ともかくカナダ映画には注目が必要です(「ユース部門」に2本新作カナダ映画を選びましたが、後日のブログで言及するつもりです)。
マキシム・ジルー監督は76年生まれのモントリオール出身で、『大いなる闇の日々』が長編4本目です。短編時代から多くの映画祭に招待されていますが、サン・セバスチャン映画祭のコンペに選出された前作『Felix and Meira』(14)で本格的にブレイクし、注目度が俄然上がりました。
『Felix and Meira』は超保守的なユダヤ系家族に抑圧される女性と、フランス系コミュニティーに暮らす男性との「禁じられた」愛を描く物語でした。家は近所なのに全く異なる世界に暮らすふたりを通じて現代社会の複雑な様相を見つめる秀作で、軽快に進行する脚本と安定した演出力も強く印象に残っています。
恋愛物語がベースにあったその前作とはガラリと変わり、新作『大いなる闇の日々』はダークな不条理スリラーでありますが、大きな社会に翻弄される個人という視点は共通しています。
時代は第二次大戦下。アメリカで仕事を終えたチャップリンのモノマネ芸人が故郷のカナダに帰国しようとする。しかし荒野の真ん中にひとり取り残されてしまい、途方に暮れる。すると親切な男が手助けしてくれるが、そこから悪夢が始まる…。
物語はファシズムのメタファーに溢れ、そのダークな主題と雄大でシャープな映像とのコントラストが興奮を誘います。あるいはアメリカという国に対する批判を読み取っていいかもしれません。監督が主人公にチャップリンを重ねるのは、『独裁者』を想起させようとしているのかもしれないし、自由の象徴たる「放浪紳士」チャップリンをアメリカが追放するのはそう遠い未来でないことを思い出させるためかもしれない…。
ビジュアルに力があるので見ているだけで面白いし、スリラーなので展開は怖いし、そしてメッセージも深読みしていくと興味が尽きません。
主演のマルタン・デュブロイユは監督の前作『Felix and Meira』の主演で国外でも知られるようになりましたが、地元のケベックでは有名な存在であるようです。不条理な事態に巻き込まれる男性のパニックを冷静に演じて説得力十分。共演陣も注目で、ロマン・デュリスやレタ・カテブといった、フランス映画ファンにはお馴染みのスター俳優が重要な役で脇を固めています。
さらに、『ザ・ダンサー』(16)に主演したフランスの女優/モデルのソーコ(Soko)が驚きの汚れ役で出演しており、そこも大注目です(ダジャレでなく)。
『ヒストリー・レッスン』(メキシコ/マルセリーノ・イスラス・エルナンデス監督)

南下してメキシコに行きます。アクの強い作品が多く集まる今年のコンペ作品の中で、『ヒストリー・レッスン』はストレートなヒューマン・ドラマにして、感動的な女性映画です。
今作が長編3作目にあたるエルナンデス監督はデビュー作の『Martha』(10)がヴェネチア国際映画祭の批評家週間に選出され、2作目『Charity』も多くの映画祭の招待を受け、アカデミー賞に相当するメキシコの映画賞では主演のベロニカ・ランガーに主演女優賞をもたらしています。そして監督は新作『ヒストリー・レッスン』にも引き続き彼女を主演に起用しました。
60歳の歴史教師のベロは、体調も優れず、引退を考えている。ある日転校生のエヴァに反抗的な態度を取られ、激しく動揺してしまう。しかしエヴァは何故かベロのパーソナル・スペースにずかずかと入り込み、家にやってきたりする。接し方を決めかねるベロは、次第にエヴァの世界に接近していく…。
ベロとエヴァのそれぞれの問題を描きつつ、やがてふたりの間に奇妙な友情が育まれ、人生にけじめをつけるロードムーヴィーへと至る展開に思わず惹き込まれます。爽やかな感動作ですと単純に言ってもいいのですが、ベロとエヴァの存在があまりにもナチュラルであり、そして彼らの旅路が日常生活の延長線上にあるため、これは我々の物語であると思わずにいられません。日常の延長が人生となり、それを紡げば歴史になるという「レッスン」…。
『ヒストリー・レッスン』を含めたこれまでの3本の作品を、エルナンデス監督は「単調さ、老い、運命、死に関する三部作」と呼んでいます。つまり、単調な日々の繰り返しの先にある老い、その先にある死、それらを束ねる運命、と言い換えてもいいかもしれません。処女作『Martha』では長年勤務した職場を追われて自殺を考える70歳の女性、そして2作目『Charity』では30年連れ添った夫婦の危機が描かれました。いずれも、市井の人々の平凡な暮らしを背景とし、観客と映画内世界は地続きにあると言えます。
なんといってもふたりの女優の醸し出すケミストリーが抜群で、不思議な相性の良さが見どころです。『最強のふたり』のように、仲の良くなるはずのなかったふたりが接近するドラマに、どうして我々はこんなに心を動かされるのでしょうね。どこかで人間関係の理想の形がそこに見えるからかもしれません。
ベロ役のベロニカ・ランガーはアルゼンチン生まれのメキシコの女優で、長いキャリアを誇る名女優です。そのフィルモグラフィーには、アルフォンソ・キュアロン監督やミシェル・フランコ監督作品も見られます。そして、エヴァ役のレナータ・ヴァカは新人ですが、ベテランをサポートするどころか、堂々たるダブル主演としての存在感を発揮しています。
本作も光栄なことにワールドプレミアの上映です。主演女優はふたり揃って来日が予定されていますので、盛大に祝福できることを願っています。
『陰りゆく父』(ブラジル/ガブリエラ・アマラウ・アウメイダ監督)

さらに南下してブラジルです。現在のブラジルでは、ホラーやスピリチュアルなジャンルとアート映画を融合させた秀作が多く作られており、新しい潮流を形成している感があります。
たとえば、2011年のカンヌ映画祭「ある視点」部門にて上映された『Hard Labor』は、食料品店をオープンしようと準備する女性が建物の異常を察知するという物語で、ヒューマン・ドラマと怪奇ものが絶妙にマッチした快作でした。これを共同監督したのがマルコ・デュトラとフリアナ・ロハスのふたりで、僕はこの流れに強い関心を抱いたため、マルコ・デュトラ単独監督作となる『空の沈黙』(16)を一昨年のコンペに招待しました。
その後、ふたたびタッグを組んだデュトラ監督とロハス監督は『Good Manners』(17)を作り、見事2017年のロカルノ映画祭審査員賞に輝いています。これまた日常のドラマと怪物ものが融合したアート映画の傑作でした。
そのマルコ・デュトラ監督が2014年に作ったホラードラマ作品『When I Was Alive』に共同脚本家として参加していたのが、今年のコンペの『翳りゆく父』のガブリエラ・アウメイダ監督です。長編監督としては『翳りゆく父』が2本目ですが、短編や脚本でキャリアを磨き、このブラジル映画の新しいトレンドを、デュトラ監督、ロハス監督とともに牽引する存在です。知り合いのブラジルの映画記者に、ブラジル映画の新しい傾向として紹介して間違いないか、と確認したところ、まさにそれがいまブラジルで起こっていることだと返事をもらったので、これは確かな情報と思ってもらってよいみたいです。
母を亡くした少女は、オカルト的なおまじないに凝っている。おまじないで母と繋がれると信じている。父親は悲しみに打ちひしがれているうえに、職場のリストラが気になり、憔悴していく。少女のおまじないと父の憔悴が合わさり、やがて不思議な事態を招いていく…。
ホラースリラーの要素もあるので、あらすじはあまり書かないほうがいいでしょうね。しかしホラー要素があるとはいえ、ホラー映画ではないです。むしろ感動的な家族ドラマであると表現する方が正しいです。このブラジルのトレンドが新潮流になっているのは、それが単なるB級ホラーではなく、アート系のドラマの中に超常現象を盛り込むことによって現実を違う側面から見ようとする姿勢が新しいからです。夫婦関係や家族関係のあり方に従来と異なる角度から光を(あるいは闇を)当てていく作品群と言えるかもしれません。
アウメイダ監督の演出も、繊細なアート映画のタッチを踏まえながら、要所に不穏なショットを挟み、とても巧みです。少女の面倒を見るはずの父が役に立たず、親子の立場が逆転してしまう様子にはユーモアも漂い、そして少女の心情に寄り添い続けることが稀有な味わいの感動へと繋がる…。うまい!
ちなみに、アウメイダ監督を見出したプロデューサーのロドリゴ・テイシェイラ氏は『君の名前で僕を呼んで』や『フランシス・ハ』などを手掛ける気鋭の存在で、これに気付いたときは思わず唸ってしまいました。
ブラジルの最先端トレンドを東京でリアルタイム体験するのも映画祭ならではの楽しみだと思います。是非目撃を!
『シレンズ・コール』(トルコ/ラミン・マタン監督)

米大陸から中東に飛びます。トルコの映画界は活気があり、若手に注目株も多く、実に作品選びに苦労します。僕は今年初めてイスタンブール映画祭に出張し、Work in Progressプレゼンテーション(完成前の作品を映画祭やポスプロ資金提供者にプレゼンする場)に出席したり、監督やプロデューサーに会ったりして情報を集め、その中で出会ったのがこの『シレンズ・コール』でした。
ラミン・マタン監督は本作が長編3本目。処女長編『The Monster’s Dinner』(11)はトルコのアンタルヤ映画祭で新人監督賞を受賞するなど注目され、続く『Impeccable』(13)は釜山映画祭でプレミアされたのち多くの映画祭を回っています。それからEUの人権プロジェクトのサポートを受けた短編を作ったのちに取り組んだのが、新作『シレンズ・コール』です。
都会で暮らす現代人にはギクリとする話です。舞台となるのは大都会のイスタンブール、それも再開発がそこら中で進行している騒がしい地域で、建設会社勤務の男はやかましい環境につくづくうんざりしている。そんな中、女友達のシレンが南部でオーガニックな暮らしを送り人生をエンジョイしていると聞かされ、思い立ったが吉日とばかりに荷物を速攻でまとめ、彼女と合流すべく街を出ようとするものの、都会に張り巡らされた結界に阻まれ、どうしても街から出られない…。
ブラック・ユーモアに満ちた風刺ドラマです。現代社会への皮肉が見事に効いていて実に痛快。我々が抱きがちな都会からの脱出願望を打ち砕き、その一方でオーガニック・ライフなるものへの幻想もバッサリと(いや、チクリとかな)斬ってくるセンスがナイスです。
近年トーキョーのコンペで上映してきたトルコ映画は、大自然を背景にしたものが目立っていました。レハ・エルデム監督の諸作品は森を抜きにして語れませんし、農村部で三部作を作ったセミフ・カプランオール監督が次に手掛けた(昨年TIFF作品賞の)『グレイン』は荒野を舞台にしたディスピアSFでした。カンヌの常連ヌリ・ビルゲ・ジェイラン監督は都会を舞台にすることはあっても多くの作品がアナトリアで撮られています。
つまり、大都会イスタンブールを舞台にしたトルコ映画を国際映画祭で見る機会があまり多くなく(『猫が教えてくれたこと』という素敵な例外はありますが)、『シレンズ・コール』は新鮮な印象を与えてくれます。もちろん、観光地としてのイスタンブールは一瞬たりとも姿を見せませんが、喧噪の中の人々の暮らしは我々には馴染みがあり、トルコ映画が一気に身近に感じられるのです。
本作もワールドプレミア上映です。トルコの有望監督、ラミン・マタン監督をお見逃しなく!
『テルアビブ・オン・ファイア』(イスラエル/サメフ・ゾアビ監督)

ここ数年、イスラエル映画に秀作が目立つことが我々選定スタッフ間の共通認識でありました。少しまとまって紹介したいと思っていたところ、イスラエル建国70年を契機にイスラエル大使館の協力が得られ、5本の特集を組むことができました。そしてコンペにもイスラエル映画の招待が叶ったことから、コンペであると同時に特集の1本でもあると位置づけた次第です。
この『テルアビブ・オン・ファイア』は観終わった瞬間に「お見事!」と声を上げたほど、脚本の上手さに興奮しました。イスラエルとパレスチナ関係のような複雑な政治状況をコメディで伝えるのは至難の業ですが、かつて『ガザを飛ぶブタ』(11)が東京国際映画祭コンペで観客賞を受賞したように、それが成功すると大きな効果を上げることがあります。その新たな好例が『テルアビブ・オン・ファイア』であります。
60年代の中東戦争前夜を舞台にした禁じられた愛を描く「テルアビブ・オン・ファイア」というタイトルの昼メロが、現代のイスラエルで大ヒットしている。そのドラマ制作現場で働くパレスチナ系のインターン青年は、日々通らなければいけないチェックポイントでイスラエル軍の係官から尋問を受け、思わず「テルアビブ・オン・ファイア」の脚本家であると嘘をついてしまう。すると係官は妻がその番組の大ファンであると語り、自分の脚本アイディアを青年に押し付けてくる…。
笑いながらエンタメを楽しみ、現地の事情についても理解が進むという実に貴重な作品です。サメフ・ゾアビ監督は、現実がシビアであるからこそ笑いで伝えることに重要性を認めつつも、軽々しくならないように慎重に気を遣います。あくまでも現実に沿い、人々の暮らしを丁寧に描写することを心掛けているとインタビューで語っています。
テルアビブとニューヨークで映画作りを学んだパレスチナ系イスラエル人のゾアビ監督は、本作が長編監督3本目。映画祭経験も豊富で着実にキャリアを積んでいます。『パラダイス・ナウ』(05)や『オマールの壁』(13)が世界中で話題となった先行世代のハニ・アブ・アサド監督との交流も厚く、2016年に日本公開されたアサド監督の『歌声にのった少年』では共同脚本を手掛けています。
主演の青年役には、アカデミー賞外国語映画賞にもノミネートされた『パラダイス・ナウ』で主役を務めていたカイス・ナーシェフ。『パラダイス・ナウ』の自爆テロに関わる深刻な役柄から一転し、本作ではひょうひょうとした雰囲気をまとい、絶妙な味わいで魅了します。
楽しくタメにもなり、イスラエル映画の充実も体感できるエンタメの逸品、お楽しみに!
欧州、米大陸、中東と巡り、次回はいよいよアジア圏に突入します。